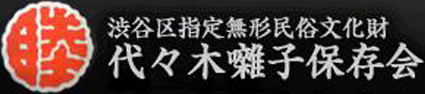【第一回】代々木囃子について
これから数回に分けて、お囃子一般と代々木囃子の歴史、代々木囃子を守る理由、楽器の構成と其の役割、舞について等、述べる事といたします。
江戸時代まで遡ることができる代々木囃子は、平成18年に渋谷区無形民俗文化財に指定されました。代々木囃子の演奏は代々木八幡宮の祭礼に於いて奉納し、地域に伝わった民俗芸能を継続し保存するのが目的です。
昔から代々木八幡で聞こえる代々木囃子の音だけが、この社の囃子の音なのです。
囃子の始まりは色々説が有って明らかではありません。一般に伝えられている説では、平安時代に流行った田楽などが鎌倉時代になると武士に相応しい勇壮な五人で行う囃子に成立して、鶴岡八幡宮に奉納されたのが始まりとされています。代々木囃子の演目も矢台または屋台(やてい)、鎌倉(かまくら)、國堅(くにがため)、師調目または仕丁舞、四丁目(しちょうめ)の名前がある曲を鎌倉時代から受け継いで演奏しているとされています。
実際には当時から随分変化しているのでしょうが、名称や音の響きも鎌倉時代の雰囲気が感じられます。
室町時代は衰えたようですが江戸時代には葛西囃子や神田囃子(江戸の祭り囃子として東京都の無形民俗文化財に指定されています)を始めとして代々木囃子も大いに栄えました。幕末に一時廃れますが、明治、大正、昭和の初期まで、かなりの発展が記録されています。
代々木囃子保存会会長 杉尾伸太郎