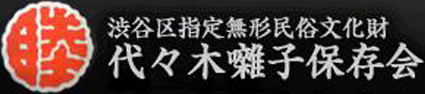『第二回』代々木囃子を守る理由
江戸の中心から、周辺部にドーナツ状に広まった囃子は、永い時間をかけて、その土地の人に依って育まれたワインや地酒の様にその土地に定着し、街の音になりました。このように独特の成熟を遂げた囃子を地域の文化として認め保護する事が、平成17年渋谷区に指定された無形民俗文化財の目的です。
代々木囃子も江戸囃子の一つの囃子として、目黒囃子の影響を受けたとしても、ここ代々木八幡宮の囃子として、定着して来た結果を守る事が、多様な文化財を守る意味です。
では、永い歴史を背負った代々木囃子の何処を守ったら良いのでしょうか。おそらく代々木囃子も時代とともに継承して来た人も変わりますから、録音装置も無い時代には、自然と少しずつ変化を遂げて来たのでしょう。
昭和30年から60年頃が現代の代々木囃子の最盛期とされています。代々木八幡宮の礼拝殿の中には昭和56年に奉納された鎌倉彫りの奉納額が掲げられており、当時の隆盛を偲ぶことができます。なお、この時代に捉えられた音源も若干残されていますので、この音源を尊重し、形は奉納額などの遺産を受け継ぎ、代々木八幡の音、更には初台など地元の街の音色として伝へ続けるのが最善の方法であると思います。
代々木囃子保存会会長 杉尾伸太郎