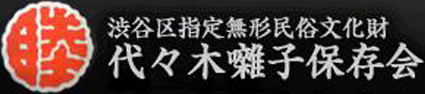『第三回』囃子の楽器の構成
代々木囃子の場合、お雛様の五人囃子とは違いますが、全体の構成は5人の囃子です。
前後2列に位置しますが、前列、向かって左に大胴(オオドウ、長胴太鼓)奏者がかっこ台に乗せた太鼓の一面に向かって座り、2本のバチで片面のみを叩き、低音のリズムを受け持ちます。
少し空けて前列中央にリズムの中心である平太鼓(シラベ)のシンが座ります。其の隣に平太鼓のナガレが座ります。シンの補佐をしますが、音程はシンより低くなっています。後列大胴の後ろに、やや控えめに立って演奏するのが四助(ヨスケ、当り鉦)で、左手で当り鉦を持ち、バチで叩いたり、擦ったりして演奏します。後列向かって右に囃子の中心である笛が全体を見渡す位置に立って演奏します。居囃子の構成は以上のとうりですが、屋台での巡行の場合は空間に依って配置が代わります。神楽殿などで舞を伴う場合、大胴と平太鼓のシンの間を空けて白狐などの舞の花道を設けることもあります。
獅子舞の為の囃子は歩行しながらの演奏も必要です。その場合の太鼓は丸一と称し、小型の平太鼓の下に小振りの長胴太鼓を取り付け、抱えて両手で叩いて演奏します。一人3役です。笛はリーダで一人、それに四助一人が伴います。
代々木囃子保存会会長 杉尾伸太郎