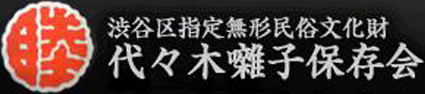『第四回』楽器について
(ア)笛
各囃子会のに実態や文献から笛がリーダに成っています。それは唯一のメロデイ楽器だからでしょう。山の手の囃子は、先ず笛の音からスタートします。代々木囃子では、笛は篠竹製の7穴で、やや低い5調子を用います。管内は漆が施され、外側に藤が巻かれています。アンブシュア(フランス語)と言いますが口の形と機能を保つ為に週に一度は練習が必要です。笛だけは浴衣での演奏が許されています。
(イ)太鼓
平太鼓のシンは笛を立てながらもメロデイに絡む様に音を大切に叩く必要がある。平太鼓のナガレは全体のリズムを刻んで囃子の土台を作り重要な役割です。笛の速度を見計らってシン共々早さを調整します。大胴は全体を引き締める低音部を受け持ちます。力自慢で叩くのではなく、大胴の音の上に多の音を載せて行く感覚が望まれます。
(ウ)四助(当り鉦)
他の4人を助けるという意味で四助と言うようです。従って4人の音に良く気配りをして当り鉦の中心や縁を叩いたり擦って曲に艶と輝きを与える様にするのが役割です。バチは以前は鯨の髭でしたが、今は竹に代わり、玉は今でもシカの角で出来ています。
代々木囃子保存会会長 杉尾伸太郎