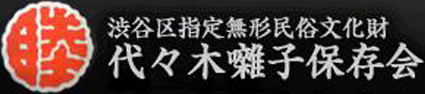『第五回』楽曲と練習について
他の江戸囃子と基本的には近く、先ず、勇壮な屋台、次にゆったりとした鎌倉、一歩ずつ行進し、次第に早くなる國堅、一転して駆け出す舞の様な師調目または仕丁舞(代々木囃子では四丁目と書かれる事が多い)、最後に最初の屋台の変形と成る屋台の5曲を演奏し、それを「ひとっぱやし」と言い、凡そ15分から20分かかります。
昇殿、子守唄などの曲も在ったようですが、現在まで伝わっていません。只、道行きや獅子舞などで用いられる印旛(インバ)または仁羽(ニンバ)は里神楽の曲と思われ、現在も良く演奏されます。
練習はボルト締めの平太鼓を用い、かなのテレツクスケテンテン等と表示された譜を見ながら口伝で学びます。
笛や四助も同じですが、今ではビデオなどで容易に口伝を受け継ぐことができるので、心配要りません。
代々木囃子保存会会長 杉尾伸太郎